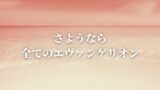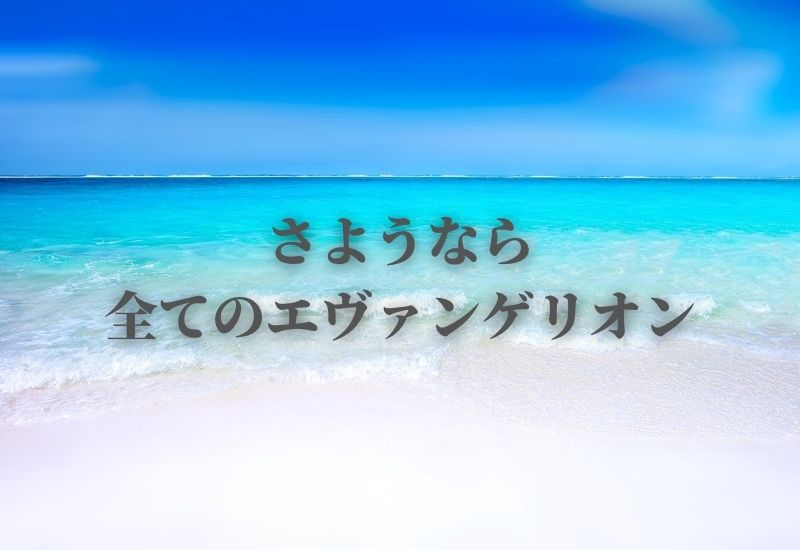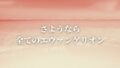「さようなら全てのエヴァンゲリオン ~庵野秀明の1214日~」<後編>では、
なぜ?エヴァンゲリオンをもう一度劇場版シリーズとして作られることになったのか?
前代未聞のスケールで描かれるエヴァの世界を完結させるという
もはや『苦行』の様な制作現場を味わえる。
エヴァの完結については様々な意見があるが私は、このドキュメンタリーと共にエヴァンゲリオン本編を見ることで演出の意味にさらに深い理解ができるのではないかと思っています。
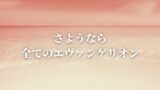
さようなら全てのエヴァンゲリオン 後編 エヴァを終わらせるということ
このドキュメンタリー後半では、庵野秀明監督の半生も語られていると共に前回のテレビ版「新世紀エヴァンゲリオン」と旧劇場版作品2作品で一度完結した「エヴァンゲリオン」という作品について庵野秀明監督本人が語っている。
私も当時、友人と旧劇場版作品を見に行った時のことを思い出さざるおえなくなった。
エヴァンゲリオン旧劇場版が上映されていた当時、アニメは一部のオタクが見るもの、子供が見るものだった。
ネットもまだ創世記で社会の中で話題に上がることも少なかった。
ただ「エヴァ」はテレビ放送の完結がそもそも謎すぎて旧劇場版で完結なるということで話題になっていたと思う。
エヴァンゲリオン旧劇場版、上映が終わった後かなり多くの人(オタク系男性がほとんど観客)がほぼ全員うなだれていたのを思い出す。
一緒に行った友人と
「やっぱりエヴァは分からんな」
っていう結論に達した。
当時のことについても今回のドキュメンタリーで庵野秀明監督本人から語られている。
当時の苦悩と葛藤がどれほどのものだったのか是非見てもらいたい。
その中で出された今回の「結末」に私はとても納得できたし、
前編のプリビズを終えた後、庵野監督が言った
「伝わってない部分は全部カットしてもいい部分だ」という意味がよく理解できる。
アニメ制作の過酷な現場が牙を剥く 「エヴァンゲリオンを嫌いにならないでください」
「周りで起こっていることで僕が何をしているか見せた方が面白いと思う」
「僕の周りにいる人が困っているのがいい」
庵野監督も言う様にドキュメンタリー的にはその方が面白い。
しかし、エヴァ制作の後半は「面白い」といっていいのだろうか?
そう思ってしまった。
監督の鶴巻さんの日々やつれていく様子と庵野監督の後ろで真っ白な灰になって立ち尽くすシーン(オープニング約60秒ごろ)は、言葉や演出では決して出ることのない
「シンの作り手」を浮き彫りにしたと思う。
CGIアニメーションディレクターの松井さんも
「庵野さんにも命削ってでも頑張りますって言っちゃたっから・・・・・」
本当に苦しい中で笑顔を浮かべながら
「ものを作るのって そういうことでしょって思うんですよね」
そう答えた。
アニメ制作の現場は「ブラック」
そんなことが有名になってしまった昨今
もはや「ブラック」を通り越して皆が「光」になっていく様な
このドキュメンタリー後半ではその想像を絶する過酷さが垣間見える。
多くの人が夢を持ち入ってきては去って行ったであろう現場
進捗状況示すデットラインがマイナスになっていく状況の中
職人の姿とコメントにアニメーションに携わる人たちの作品に対する「信念」が伝わってきた。本当にカッコイイ。
CGI監督の鬼塚さんも
「エヴァンゲリオン好きでってきてくれる人にエヴァンゲリオン最後まで好きでいてください 嫌いにならないでください」って初めにいうのだそうだ。
さようなら全てのエヴァンゲリオン
エヴァンゲリオン完結版となった「シン・エヴァンゲリオン劇場版」は、多くの付箋を回収し分かりやすく、伝わりやすく完結した。
それは、このドキュメンタリーを含めてだと私は思う。
庵野監督も作中で語っているように近年では、「謎のまま」が良いという人が減ってきている。
ドラマも分かりやすく役者の演技もカットも構成も変わってきた。
アニメや漫画にもその流れは押し寄せてきてる。
テンポのよい構成と伝えることを伝えやすくする手法はセリフ回しも変えてきた。
最大の「謎アニメ」であるエヴァンゲリオンを終わらすには最後の時期だったのかもしれない。
「シン・エヴァンゲリオン劇場版」を映画館でみた後
今回は、私も言えた気がする
さようなら全てのエヴァンゲリオン