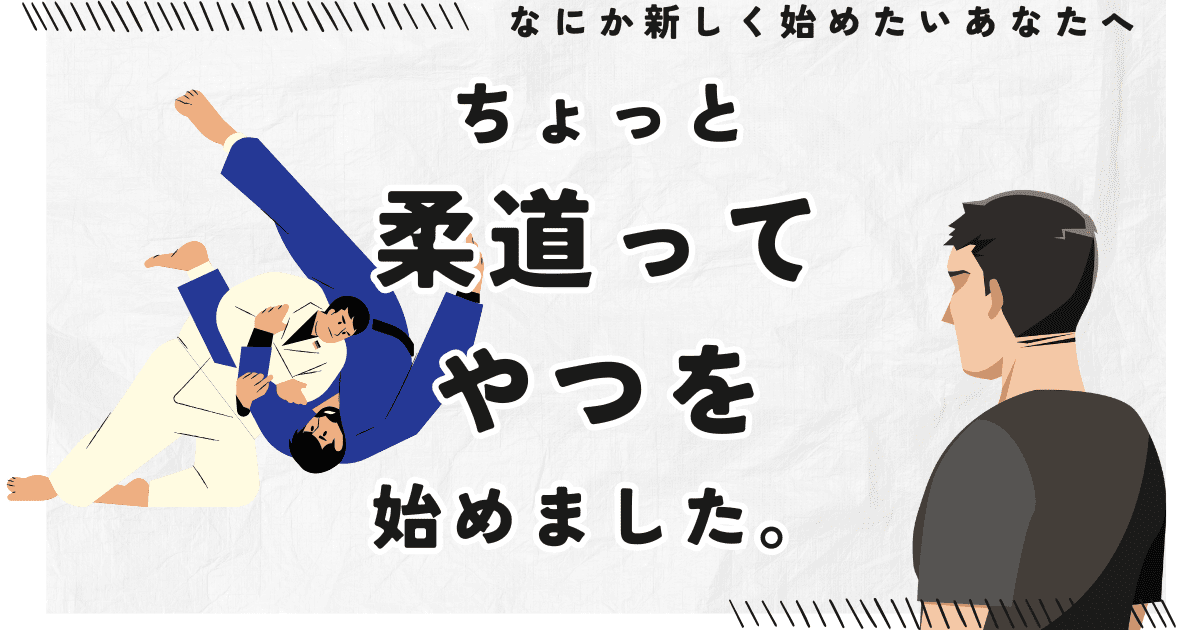こんにちは!
かじる。みつける。新しい自分。
どうも!初心者代表、メープルです。
今回は、柔道(JUDO‼)が、始めてみたくなるような情報をお届けします!
柔道といえば、オリンピックでしょうか?
実は、もっと身近な存在だったのではないでしょうか?
みなさんも、学校の体育の授業で「柔道」一回はご経験ないでしょうか?もしくは、体育の選択で、ダンスか柔道、また武道として、柔道、剣道、空手のなかから選びなさいと、柔道をやるかやらないか、考えた経験はあったのではないでしょうか?
柔道のイメージはどうですか?泥臭い?ごっつい人たちのスポーツ?なんだか厳しそう?
柔道とは、これ!と思う試合を見ていただきたいです!
(ぜひ、音声付きで!!ゆるい実況も併せてお楽しみください)
かっこいい!
柔道は男女年齢関係なく始められて、生涯柔道として長く付き合える武道です。
定年後、体力づくりとして始められた65歳の方が3年後には黒帯になれたり、としっかり自分の柔道を持つことができると長く楽しく続けられます。
次に、昔やっていた主婦の方が柔道を始めるというプロモーションビデオがありましたのでお伝えします。かっこいい編集です!
とはいっても、改めて柔道とはどんな武道?スポーツ?
魅力はなんなの?大人の初心者が始めるにはどうしたらいい?などなど
そんな疑問を、わたし、メープルリーダーが全力で、お届けいたします!
柔道とは!?
柔道の語源は、鎌倉時代まで遡ります。
柔道の起源は、12世紀以降に生まれた「柔術」だと言われています。柔術は、戦の場で相手と接近して戦う「組み討ち」(くみうち)を想定した武術で、武士が体を鍛える手法のひとつとして武家社会のなかで発展し、江戸時代までにいくつかの流派が生まれました。
しかし、1868年(明治元年)に明治時代が始まると、日本人の生活に西洋の文化が取り入れられるようになった結果、古くから続いていた柔術の勢いが失われてしまいます。
そこで、嘉納治五郎は、柔術を新しい形に生まれ変わらせることで、再興を図りました。日本に伝わる複数の柔術を学び、各流派の長所を研究して新しい技や指導体系を確立。原理となる「道」があってこそ「術」(技術)が生まれるとの考えから「柔道」と名付けました。
長い歴史がある柔道。
オリンピック競技として、4年に1回は、テレビ、ニュースで注目を浴び、「一本!」とダイナミックに技を決めている選手の姿を見たことある方も多いかと思います。
柔道といえば「一本!」
(一本とは、柔道の試合で相手から技を決め、一本勝ちという勝ち方で試合を終えること)
スカッとする1本!を集めた動画がありましたので紹介します!
技の名前とともにきれいな1本がまとめてあります。
すかっとしますね!!!
まあでも、ちょっとどこか、距離のあるスポーツ...。
今、柔道が始めやすい?!
今回柔道にした理由としまして、現在、柔道を始めやすい環境だと思います。
柔道の人口は、徐々に減っており、
1990年代25万人であった柔道人口は、2003年には、20万人前後、2021年までの17年間で12万2,000人にまで減少しています。2020年(令和2年)には新型コロナウイルスの感染拡大により、大きく人口が減少しています。
そのため、柔道連盟、地域の道場も競技人口の減少の課題に取り組んでいます。
初心者に優しく、「やったことがないけど始めてみたい」という気持ちを大切に、入門者として、基礎基本から丁寧に対応してくれることでしょう。
また、こんな傾向もあります。先ほど、柔道競技人口は減っているとお伝えしましたが、社会人のみの人口で見てみると、2004年から安定的に人口を維持しています。2019年には、調査期間の最高人数である約2万5,000人になっています。
この理由として、社会人選手として柔道に携わった人はそのまま継続することも多く、また、生涯スポーツとして新たに柔道を始める人がいることも要因と考えられます。
社会人から柔道を始めることに抵抗感は必要なく、やってみたいという気持ちだけで、護身術として、生涯スポーツとして、柔軟も体幹も総合的に鍛えられる格闘スポーツとして、始めてみてはいかがでしょうか?(^^)
柔道を始めるメリット!
それでは、柔道を始めるメリットについて詳しく説明していきましょう!
日常生活での怪我の防止になる
柔道の基本である受け身を習得することによって、転倒時自然と体がけがをしない転び方へと動きます。
わたくしも、中学の時に教わった柔道の受け身を体が覚えており、盛大につまずき大きく転んだ際にもしっかりと、柔道の基本、背中から落ち力を逃がすような体裁きを行い大事には至らなかった経験があります!
護身術として
柔道の技、投げ技、締め技、関節技を学び、習得することで、自分の身を守ることもできます。
礼儀作法が身につく
普段の生活ではあまり意識することがない姿勢や礼儀。柔道では、「礼に始まり礼に終わる」常に美しい姿勢を意識して、礼儀を行うことで、身も心もきれいになり、日常の自分自身の礼儀作法が柔道を始めて変わります!
体幹が強くなる、体が柔らかくなる
柔道は全身運動です。柔道を通して体の動き方を学び、全身の筋肉を使い、体感やバランス感覚が養えます。高い意識で準備運動をしっかり行うことで、継続的なストレッチとなり、関節の可動範囲がひろがります。
最近柔道、始めて見たんだと、言える
柔道を始めて、目指すところは初段でしょうか。ただ、初段を目指すには、なかなかハードルが高いようです。見学に行った際に、週一回継続的に来れて2年かなと言われました。(社会人で始めて昇段審査をうけるには)(メープル体験談)
ジム感覚で始めるには初期投資、維持費が安い
練習頻度にもよりますが、月額6000円以下が多く、2000円、3000円のところも多くありました。詳しくは、のちほど。
柔道の醍醐味!
なんといっても、柔道の醍醐味は、
相手からの美しい「一本」を取ること。
柔道は、「相手を崩してから技を掛ける」ことが基本となります。どう相手を崩すのか。実は、始め!の合図から、様々な駆け引きが行われ、組み方、力の入る方向で、次に来る動きを読みます。先に相手の重心をブレさせることができたとき、相手の不安定な姿勢に自身の技が入り、見事と「一本」が決まります。だからこそ、読みと読みの攻め合い。一瞬の隙も許さない緊張感が生まれます。
そこからのほんの少しの力で、相手が舞い、投げ飛ばされ、数秒前には正面にいた相手が、美しくきれいに畳へと落ちていく。
この感覚は、柔道でしか感じることのできない感覚でしょう。
逆もしかりです。一瞬で、気づいたら天井を向いていることもあります。何があったのだろう?そう思えざる負えない一瞬の出来事がコマ送りのように思い出される武道、それが柔道となります。
具体的な柔道の一本解説動画
体験1回目でどこまで味わえるか
体験にいってきました。
まず、運動ができる洋服で参加し、準備運動から参加しました。
20分ほど入念な準備運動、(屈伸から始まり、首のストレッチ、前屈、など)
その後、畳の端に並び、前転、後転、開脚前転と指導者の先生の号令のものと行われます。
その後、受け身を行っていきます。
このような受け身などが続きます。
この際も、見様見真似で流れに合わせてうごいていました。
一通り、全体での体のほぐしが終わると、レベル別に分かれて練習を行います。初心者は、先ほど行った受け身の練習を行うため、指導者の先生のもと受け身を体に覚えさせるため、練習を行ったり、受け身の意味を解説してくれました。
体験では、
寝技の抑え込まれた側をしたり、
立ち技では、大外刈りを教えてもらいました。
寝技の乱取り、立ち技の乱取りは、練習の風景を見学して、
ストレッチ 一列に並んで
「黙とう」
最後に「姿勢を正して礼」「正面に礼」「先生に礼」「お互いに礼」「ありがとうございました。」といい、片付け、掃除を行い、2時間の体験がおわりました。
参考動画 大人も子供も始め方に違いはありませんね。(^^)
・実際に行うには
まず、お近くの柔道場を探してみましょう!
対象者が書いてあるので、社会人と書いてある道場を選びました。
問い合わせ担当者(メールアドレス)が記入してあったので、
問い合わせメールを行うと、「大歓迎です。いつでも見学に来てください」と、返信があり「いついつに伺います。」と連絡。持ち物や注意事項を聞いて体験にいきました。
柔道着は、相談を行うと貸してくれる場合もありますが、
購入も今はネットで簡単に4000円ぐらいから購入できます。
・最後に
柔道を始めて、初めて一本が取れた時の相手、感覚、驚きは、忘れもしません。
柔道は、ほかのスポーツと違って、武道「心技体を一体として鍛え、人格を磨き、道徳心を高め、礼節を尊重する態度を養う、人間形成の道」の中のひとつです。
大人になって忘れかけていた、礼儀の大切さや美しさを思い出させてくれます。
「礼に始まり礼に終わる」
柔道をすることで、心を整え、日々のストレスや喧騒から解放される瞬間を得られます。
ただ体を動かすだけでなく、目標を持ち練習、同時に礼儀作法を身に着けながらも、自分の内面も磨けるのも魅力の一つです。
柔道を通して「強さ」「優しさ」を兼ね備えた自分に出会えるかもしれません。
新しい一歩を踏み出して、日常でまだ見ぬ自分と出会ってみませんか?